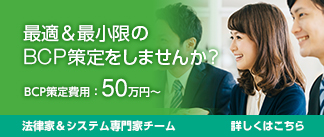BCPで必要な「経営資源の把握」のポイント
2017.05.14更新

今回は、BCPを策定するために必要な事前準備のひとつ、経営資源の把握についてです。
経営資源の把握
BCPを策定するために、まずはBCPを策定しようとする企業の経営資源を把握する必要があります。
経営資源とはいわゆる「ヒト」、「モノ(及び情報)」、「カネ」を指しますが、具体的には、役員や従業員、車や営業所、倉庫や倉庫内にある在庫、企業が保有する情報、キャッシュなどがこれに該当します。
1.「ヒト」の把握
ここで言うヒトとは、主に役員や従業員を指します。
経営者の方や人事・総務部などは、各役員や従業員がいつもどのような業務を担当しているかについては当然に把握していると思います。
では、BCPの観点からみた各役員・従業員の強みや弱みまで把握できているでしょうか?
各役員・従業員の強みや弱みまで把握できていますか?

例えば、通勤距離などもひとつのポイントになるでしょう。
地震などの災害時でも歩いて会社に来れるような従業員がいれば、それはBCPにおいて強みになるでしょうし、いくら優秀な従業員でも通勤に2時間かかるような場合はBCPにおいて弱みとなるかもしれません。
BCPが実行される場面では、通常業務よりもシビアに強みを活かすような人員配置が求められます。
具体的には、後に決定する「主要業務」を少しでも早く復旧させるため、「誰」が「何」を「何名」で行うかなどをBCPに定めます。
大きな会社では「◯◯の資格を有する3名が△△業務にあたる」とか、「経験年数◯年以上の正社員2名が△△業務にあたる」といった感じになると思いますが、中小零細企業では、「AさんとBさんが△△業務にあたる。Aさんが出社できないときは、Cさんを代わりとする。」などと定めても良いと思います。
2.「モノ(及び情報)」の把握
ここでいうモノとは、企業が保有(賃借)している、資産(車や営業所、倉庫、倉庫内の在庫など)、電気・水道・ガスなどのインフラ、情報などを指します。
モノを把握することは重要です。
実はBCPで守る経営資源の大半はモノだからです。
BCPで守る経営資源の大半はモノ

運送会社が車を失ってしまったら本業ができなくなりますし、倉庫業者の倉庫が損壊してしまっても本業ができなくなります。
インターネットや電話が使えなくなったら、大多数の事業に影響を与えることでしょう。
まずは「モノ」をリスト化をしましょう!
リスト化すると、自己で守ることができるモノ(企業の保有資産などの「内部資源」)と自己で守ることができないモノ(インフラなど外部から供給を受ける「外部資源」)とがあることに気づきます。
BCPを策定する場面では、内部資源を如何に守るか、外部資源を如何に調達するかを定めていくことになります。
また、企業が保有する「情報」についてもリスト化して、企業がどのような情報を取り扱っていて、日常業務を行うにはどのような情報が必要か、などを把握すべきです。
企業が保有する「情報」についてもリスト化
ここでいう情報とは、総務や経理に関する情報、業務に関する情報、顧客(取引先)情報などが該当します。
例えば、紙ベースではなく、全ての情報をデータで管理しているとしましょう。
災害の発生に伴い、その情報が参照出来なくなったり、失ったりした場合には事業が停止し、業種によっては致命的なダメージを受けてしまいます。
士業なども情報が参照できないと、何もできなくなってしまうのではないでしょうか。
意外と見落としがちですが、BCP策定の事前準備の段階で、保有情報の管理状態、バックアップ体制、内容等についてしっかり把握しておきましょう!
3.「カネ」の把握
企業にとって、お金は極めて重要です。生命線です。
お金が無いとヒトも採用できませんし、モノも保有できません。
結果、当然に事業も継続できません。
BCPを策定する際には、お金がいくらあるかということも重要ですが、ここで最も重要なのは、財務状況の把握です。
最も重要なのは、財務状況の把握
仮に今災害が発生して、事業が停止したときに、どこにいくら使えるか、人件費や支払い等、キャッシュはいつまでもつかなど、現状を正確に把握しましょう。
策定時点ではキャッシュがあったけど、災害発生時にキャッシュが無い!なんてこともあるかと思います。
事業が停止した際に最低限必要となるキャッシュ、資金繰りの方法などを予め検討しておきましょう。
次回は「主要業務の検討」についてです。