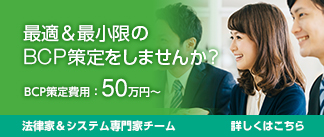主要取引先リストアップと目標復旧の設定
2017.05.29更新

今回はBCPを策定するために必要な事前準備についての「主要取引先のリストアップ、分析」と「目標復旧レベル、目標復旧時間の設定」について書いていきます!
主要取引先のリストアップと分析
BCPを策定するにあたって、多くの業種はサプライチェーンにについて無視するわけにはいきません。
(※サプライチェーンとは、「各企業の役割分担にかかわらず、原料の段階から製品やサービスが消費者に届くまでの全プロセスの繋がり」のことを言います。)
原材料の調達から販売までの間において、どこかが分断してしまうと事業の継続に影響が生ずるためです。
企業のビジネスモデルによるところはありますが、例えば製造業を営んでいて、仕入先において災害が発生したために材料が供給の調達ができなくなったら・・・、その材料はなかなか代替できないものだったら・・・など、製造業者自体が災害にあっていなくても取引先が被災することによって事業に影響が生じることも考えられます。
そのような事態に備え、あらかじめ主要取引先との取引実績、取引先の代わりは存在するか、取引先はBCPを策定しているかなどを分析し、把握しておきましょう。
具体的には、次のように整理するとわかりやすいと思われます。
1. 仕入先のリストアップとその取引内容、有事の際の代替可能性
製造業などでは、材料の調達ができなくなってしまうだけで、事業がストップしてしまう可能性があります。そのような場合に備えて、どこの仕入先から何パーセント程度の材料を調達しているか、その材料は他からも調達可能かどうかなどをリスト化して、把握しましょう。
2. 外注先のリストアップとその取引内容、有事の際の代替可能性
ある製品を完成させるために、業務の一部を外注することもあると思います。または材料や製品の運搬を運送業者に依頼することもあるでしょう。
BCPを策定する際には、これらについてもリスト化して、代替手段の有無などまで認識しておくことが大切です。
3. 得意先(納品先等)のリストアップとその取引内容
製品の納品先(顧客等)もリスト化しておきましょう。次で紹介する目標復旧レベルを検討するにあたって重要な情報となります。
例えば、A社との取引実績は安定しているがB社との取引は波がある、C社とは過去にトラブルがあったなどの情報がリスト化されていれば、有事の際はA社との取引を優先させるなどの判断ができるはずです。
目標復旧レベルと目標復旧時間の検討、設定

BCPを策定するための事前準備として、実際にBCPを実行したときの目標復旧レベルと目標復旧時間を検討し、設定しましょう。
ここでは、経営資源への影響レベルに応じて、最低限度復旧しなければならない事業の範囲(レベル)と、その事業を復旧させるまでの時間を設定することが目的です。
目標復旧レベルを検討することが重要で、主要業務全てを復旧させるための時間を算出するだけでは不十分です。
主要業務を特定したとして、その主要業務を100%復旧させるための時間を定めるだけでは、復旧させるためのステップが複雑化、膨大化してしまい、その結果、実行困難なBCPとなってしまう可能性があるからです。
最低限度復旧しなければならない事業の範囲(レベル)を検討するための基準として、次のような項目で考えると検討されやすいかもしれません。
製造業の場合
- 生産量
- 生産する製品群
- 提供先
運送業の場合
- エリア
- 貨物の種類
- クライアント
IT系のサービス業の場合
- 処理能力
- 利用可能なユーザー数
- ユーザーが利用可能な機能の範囲
目標復旧時間の検討
目標復旧レベルを決定しましたら、次は目標復旧時間の検討に移ります。
目標復旧時間を計算するために、まずは主要業務及び目標復旧レベルをクリアするにあたっての最大許容停止時間を確認しましょう。
業務が停止しても致命的とならない最大時間を認識したうえで、その時間以内の目標復旧時間を設定しないと意味が無いからです。
目標復旧時間の検討は、もちろん自社の財務事情に基づく場合もありますが、対外的に主要業務に関わる取引先との関係や、サプライチェーンの要請などの観点からも検討する必要があるでしょう。
従って、目標復旧時間は、次の要領で設定すると進めやすいかもしれません。
- ① 目標復旧レベルの設定
- ② 最大許容停止時間の検討
- ③ 自社の財務事情、対外的事情の検討
- ④ 目標復旧時間の検討、設定
前々回、前回、今回はBCPを策定するための事前準備について書いてきました。
これらの検討事項全てを通常業務を行いながら企業内で進めるのは大変だと思われますが、良いBCPを策定するためには大切な事ばかりです!
企業内で進めるのが困難な場合は、外部の専門家に相談されるのも良いかと思います。